どこが出題されるかわかってしまう「3つの判断基準」とは?

こんにちは、セニョール中原です。今日もお付き合い下さり、ありがとうございます。
「ツボ式学習法」は、試験に出るところを自分で判断できる基準を教えてくれる、という話の続きでしたね。
この基準は、大きく分けると3つの基準から成り立っています。

この基準のうち、1つは「過去問」です。
まあこれは、社労士受験生なら誰もが押さえていることだと思いますので、ここに書いちゃいました。てへっ。
(ていうか、販売ページの説明に過去問のことは書いてますし)
えっ、過去問をちゃんと押さえていないって?それはいけませんねえ(偉そうに)。
社労士試験に限ったことではありませんが、試験というものは「過去問」から繰り返し出題される傾向がありますので、過去問はしっかりとマスターしておきたいところです。
しかし、社労士試験の場合、過去問から出題される割合が年々減ってきています。
このことは、過去問だけをしっかりマスターしても合格ラインに届かないことを意味します。
では、過去問から出ないところは、どうやって勉強すればいいのでしょうか。
それこそ、しらみつぶしに勉強する必要があるのでしょうか。

そんな必要はありません。人生は長いようで短いのです。
そんな試験に出るかでないかわからない部分を膨大に覚えるのは、貴重な時間をどぶに捨ててしまうことになってしまいます。
そういう無駄な時間を過ごさないでいいように、「ツボ式学習法」は、過去問以外の部分でどこが出るのかの判断を自分でできるような基準を教えてくれます。
ですから、あとは基準に適合した部分を勉強すればいい、ということになります。
過去問以外の出題部分を知る。
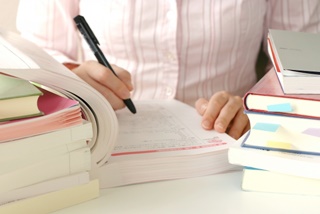
この、過去問「以外」の残り2つの基準。これがとても重要というわけです。
過去問以外の部分で、どこが出るか解らないから、テキストの膨大な量を勉強しなければならない羽目に陥るのです。
ですから、この2つの基準さえ知れば、もう社労士試験を突破したも同然?…ちょっと気が早いですかね。

この基準ですが、これをここで公表!
…してしまうと坪先生に怒られてしまいますので、これ以上は公表できません…
少なくとも1つは、私は全く思い至らなかったような基準ですね。
ははあ、なるほど、このような方法で出題される部分を選別するのか。
まだまだ私は研究不足でしたね。そりゃ坪さんとはキャリアが違います、キャリアが。
私のようなペーペー受験生では、とても太刀打ちできません…
さあ、ついに私は社労士試験合格への丸秘情報、プラチナチケットを手に入れてしまいましたよ。
これさえ知ってしまえばもう恐いものなし、早速勉強開始だ!

…いやいやその前に、まだやることがあります。
この基準自体はある意味抽象的ですから、これだけではどこを勉強すればいいのか、まだあいまいなんです。
ですから今度は、その基準にしたがって、どの科目のどの部分が出題されるかを明確にする作業が必要なんですね。
そのために、著者の坪先生は、自分だけの「オリジナルテキスト」を作りなさい、といいます。
えっ、オリジナルテキスト?それはいったいどのようなものなのでしょうか。
というわけで、今回はここまでと致します。
ご静聴戴き、ありがとうございました。(ペコリ)

