満点は不要、でもあなたの勉強法は「満点を狙う」勉強法になってませんか?

合格のため、満点取る必要はない…
誰もがわかっているはずです。しかし、わかっているはずなのに、実際に行っている勉強法は、満点を取りに行くような勉強法になっていることがよくあります。
この「ツボ式学習法」も、満点を取る必要はない、試験に出るところだけを勉強すればよいと言っています。
「それはごもっとも。でも、どこが出るかわからないから苦労しているんじゃないか」
「出そうなところだけを勉強しても、選択式で変な問題を聞かれて答えられなかったら、それだけで足切りに遭ってしまうんだぞ」

…その気持ちは痛いほどわかります。かくいう私も、選択式での足切りを経験していますので。
しかも、みんなが答えられた科目で足切りを食らったならしょうがありませんが、正答率の低い科目で足切りを食らってしまった場合は、「もう隅から隅まで勉強するしかない」という気持ちになってしまうのも、無理はありません。
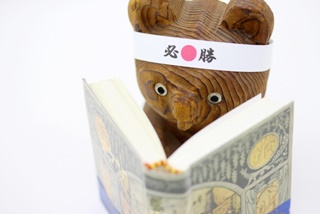
しかし、それはやはりどう考えても非効率です。
司法試験でさえ、合格者はそのような勉強をしていません。
やはり、勉強すべき事項を絞って、試験に出るところだけを確実に抑えていくほうが、合格可能性ははるかに高まるのです。
「…だから、その試験に出るところがわからないって言ってんの!」
…はい、たしかに。試験に出るところがわかれば、どんなにいいことか。
後はそこをしっかり勉強すれば、合格したも同然なのですから。

その「試験に出る部分」を明確に教えてくれるのが、「ツボ式学習法」というわけです。
予備校が絶対に教えない、その理由は?

「え〜、本当か?そんな都合のいい話があるのか?」
もちろんこの「ツボ式学習法」に、「労働基準法20条1項ただし書が出る」などというような、細かく具体的にどこが出ると直接書いてあるわけではありません。

教えてくれるのは、試験範囲の中からいったいどこが出るのか、というのを「自分で判断できる基準」なのです。
そもそもテキストには、試験に出ない部分が膨大に書かれてあります。
なぜなら、仮にその年の試験に出た問題がテキストに載っていなかったら、「使えないテキスト」という烙印を押されてしまうので、どうしても網羅的にテキストに載せてしまうからです。
また、予備校の講義だったら、本当に出る部分だけ教えていては講義回数が減ってしまい、受講料をあまり多く取れないという事情もあったりします。

このように、販売者側の「大人の事情」が絡んでいるんですね。
その「大人の事情」に載せられて勉強していては、予備校や販売者の「集金システム」にグルグル載せられてしまい、合格が遠のくことになってしまいますよ。
ですから、その予備校や市販のテキストから余計な情報を削ぎ落として、本当に出題される可能性が高い部分だけを勉強する必要があるのです。
そしてその選別を「自分でできる」ようになる基準を、「ツボ式学習法」は教えてくれるのです。
こんな基準は、予備校はわかっていても絶対に教えてくれませんよね。
自分で自分の首を絞めることになりますから。
ベテラン講師であり、社労士試験の全てを知り尽くしている坪義生さんは、本当に試験に出る部分がどこかわかっています。
しかも、この「ツボ式学習法」を執筆するにあたり、予備校とは離れた立場で執筆したからこそ、予備校では絶対に教えられないことを書いています。
また、一般書籍では公表せず、あまり多くの人の目につかないような形で公表しているので、こんな基準を伝えられるのでしょう。

あれっ、それを考えると、私がこうやってツボ式学習法のことを書いていいんでしょうかね…
私のせいで販売停止になったらスミマセン。
販売停止になる前に、こっそり入手しておいてください。
ちょっと長くなってきましたので、ここで休憩を入れましょうか。
まあまあ、一杯いかがですか?

それから、せっかくここまでお付き合い頂きましたから、もう少し出題基準について詳しく触れることにしましょう。
どこまで書いていいのかな…
